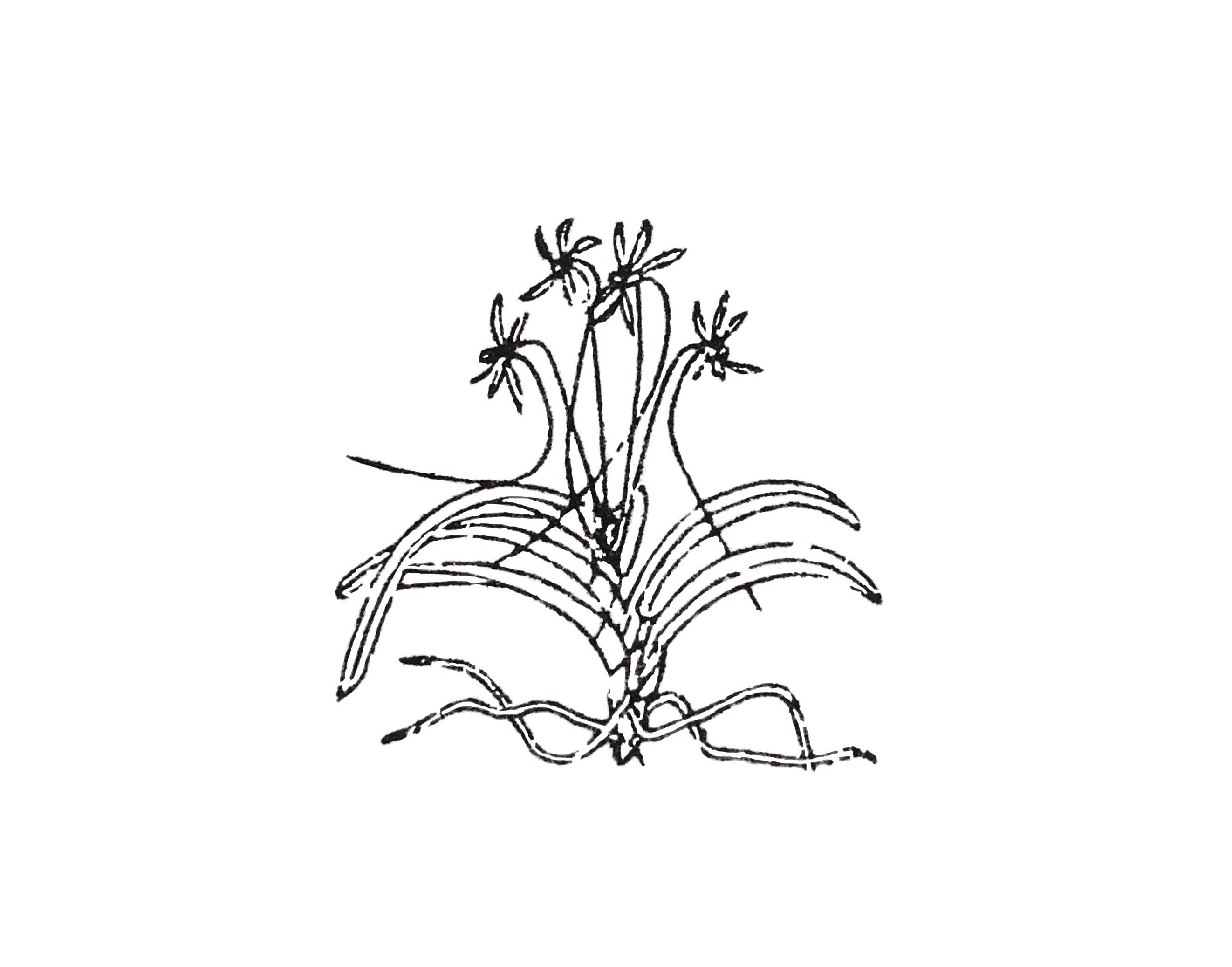テキストを入力してください
-

白蓮短歌
¥25,000
*七日一巡り 1階広間 展示品 額は別途
-

泉
¥40,000
*七日一巡り 楓の間 展示品 F4 333×242mm
-

水
¥4,000
*七日一巡り 杉の間 展示作品
-

風の景色1 / 朝、海を眺める人に吹く風
¥28,000
material | 竹紙・墨 / 表装:柿渋染布 size | 594×420 ㎜ (A2 size) ※パネル張、紐付き _2019 *七日一巡り 松の間 展示作品 <釈文> (右から) 日 海 望 ========================== 風の景色 series 2019年の自分が身を置くこの大分の地をテーマにしたシリーズ。 時間の経過と重ね合わせながら自分が感じる景色を表現した。 表装に使用している布は温泉染研究所の行橋智彦氏の手によるもので、 柿渋を染料としながら、使用する媒染や染める回数、日光に当てる時間の変化によって 8枚の柿渋染の色が茶から黒のグラデーションになっている。 その色から着想を得て別府で感じる風の景色を言葉にしつつ 墨で表現した。
-

柳原白蓮『指鬘外道』序 へのオマージュ_1
¥37,000
size/ F6 318×410㎜ material/ 画仙紙、墨、金箔 額装 *七日一巡り 竹の間 展示作品
-

風の景色6 / うつくしき地獄に吹く風
¥28,000
material | 楮紙・墨 / 表装:柿渋染布(温泉染め) size | 594×420 ㎜ (A2 size) ※パネル張、紐付き _2019 *七日一巡り 杉の間 展示作品 <作品内容> 川端康成 『千羽鶴』波千鳥 より引用 ======================= 風の景色 series 2019年の自分が身を置くこの大分の地をテーマにしたシリーズ。 時間の経過と重ね合わせながら自分が感じる景色を表現した。 表装に使用している布は温泉染研究所の行橋智彦氏の手によるもので、 柿渋を染料としながら、使用する媒染や染める回数、日光に当てる時間の変化によって 8枚の柿渋染の色が茶から黒のグラデーションになっている。 その色から着想を得て別府で感じる風の景色を言葉にしつつ 墨で表現した。
-

柳原白蓮『指鬘外道』序 へのオマージュ_6
¥30,000
size/ F6 318×410㎜ material/ 画仙紙、墨、金箔、温泉、胡粉 *七日一巡り 欅の間 展示作品 二つセットで55000円 ====================== <釈文> たとえ 三十一字も綴るすべは存じませんでも それが ほんの 生きている間かぎりに 果敢なく消えてしまうものでありませうとも 人間としての幸いの方が 望みなので御座いました よしや これが 私の為めには 万人に慕はれるほどの仕合せと なりましょうとも ==================== のちに二度と来ないと歌った別府の地で 山を見、海を見、温泉に浸かってあの頃彼女は何を感じていたのか? 約100年前、彼女が見た景色を、私も今見ている。 彼女の三十一文字、6㎝×36㎝の短冊の世界は、 まるで火と水と大地のめぐりによって噴出する温泉のよう。 このような人が生き抜いた事実も含めすべてがこの世の恵みであり、 希望である。(人はいつの時代も表現者の勇気に救われてきた) * 大正9年発刊の戯曲『指鬘外道』の序文もまた、 白蓮34歳の頃にこの別府の地で書いた文章である。 燃え上がる炎のような創造性と、 それを自ら水に流して亡きものにしてしまおうという思いとを行き来しながら 日々の苦悩を美しく謳い上げた珠玉の文章だ。 その混沌に差す光は、 時間や空間を越えて幾重にも重なって層を成し、 確かな手触りとなって、今、私の目の前に現れる。 * 本作では、その質感とエネルギーの総体として、別府温泉のスケール(温泉成分が固形化し堆積物となったもの)を用いて表現した。白いスケールは青い湯が美しい別府市小倉にある“別府 おぐら”衛藤直子様にご協力、ご提供いただいた。
-

柳原白蓮『指鬘外道』序 へのオマージュ_5
¥30,000
size/ F6 318×410㎜ material/ 画仙紙、墨、金箔、温泉、胡粉 *七日一巡り 欅の間 展示作品 5.6二つセットで55000円 ========================== 〈釈文〉 柳原白蓮『指鬘外道』序より 神様! お礼を申します 悲哀ある所 これ聖地 涙の流るヽ日は これ聖日 と 斯う 私はいつかあなたから 教わりました それ故に 今 このように 身も 魂も 唯一人の むき出しの 私が 涙ながらに 感謝の祈りを 捧げて居ります という口の下から けれども 神様! 私の本当の願いはそうではなかったのです ====================== のちに二度と来ないと歌った別府の地で 山を見、海を見、温泉に浸かってあの頃彼女は何を感じていたのか? 約100年前、彼女が見た景色を、私も今見ている。 彼女の三十一文字、6㎝×36㎝の短冊の世界は、 まるで火と水と大地のめぐりによって噴出する温泉のよう。 このような人が生き抜いた事実も含めすべてがこの世の恵みであり、 希望である。(人はいつの時代も表現者の勇気に救われてきた) * 大正9年発刊の戯曲『指鬘外道』の序文もまた、 白蓮34歳の頃にこの別府の地で書いた文章である。 燃え上がる炎のような創造性と、 それを自ら水に流して亡きものにしてしまおうという思いとを行き来しながら 日々の苦悩を美しく謳い上げた珠玉の文章だ。 その混沌に差す光は、 時間や空間を越えて幾重にも重なって層を成し、 確かな手触りとなって、今、私の目の前に現れる。 * 本作では、その質感とエネルギーの総体として、別府温泉のスケール(温泉成分が固形化し堆積物となったもの)を用いて表現した。白いスケールは青い湯が美しい別府市小倉にある“別府 おぐら”衛藤直子様にご協力、ご提供いただいた。